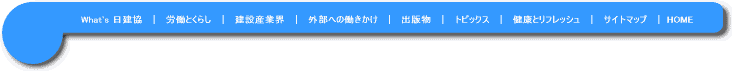
大江戸の職人気質 鳶(とび)は昔のアイドル 今なお生きつづける儀式 設計図面は私たちの手紙
手書きからコンピュータグラフィクスへ消してはならない建設産業の火
これからの建設産業に思う
現代の大都会東京を見ると、高層ビル、高速道路、ハイテク通信施設など、さまざまな社会資本が整備されています。かつて、東京が江戸と呼ばれていたころ、人々はどのようにして国づくりをしてきたのでしょうか。
気概に満ちた先人達の文化を探り、また、古くから受け継がれる独特の儀式や技術の進歩にも触れ、建設産業の今後について考えてみようと思います。
大江戸の職人気質 今ではあまり聞かれなくなった“職人”という言葉。江戸時代の代表的職人といえば、大工、左官、仕事師ですが、それ以外にも約百四十種類もの職人がいました。なかでも伝統と気概で江戸の花形だったのが、大工、左官、鳶(とび)の三職でした。彼らは大空のもと、大江戸を築き上げていった建設者であったため、「華の三職」ともてはやされました。彼らは誇り高く、粋(いき)で威勢がいいという特性をみずからつくりあげましたが、その反面、軽率で、おっちょこちょいで鼻っ柱ばかり強いという欠点もあわせもっていたのです。
大 工 左 官
そんなふうに彼らを仕立てたのは、修業時代の精神的、肉体的な苦労でした。大工を例にとると、まず、十二から十三歳で親方に弟子入りし、朝は掃き掃除から飯炊きとこき使われます。早い者で一年、普通でも二年間は、こういった下働きが続くのです。その後、親方の許しを得て、弁当持ちで仕事場に出かけますが、道具の名前を教わる程度で、あいかわらず仕事の内容といえば木屑集めか雑用でした。
夕方になれば、風呂焚き、飯炊きと追い回され、ちょっとでも動作が鈍いと、やれ 「まぬけ」 だの 「うすのろ」 だのと親方に怒鳴りまくられ、ヘマをしようものなら往復びんたが飛んできて、容赦なく飯ぬきの罰が待っていました。現代にも似たようなスパルタ教育を売り物とする団体がありますが、現代人がこの仕打ちにどれだけ耐えられるでしょうか。
江戸時代の天守工事(作事)
その後、八年目で半人前になれるといわれ、それまではタダ働きだったものが、この頃から、祭りの時期には小遣い銭がもらえるようになり、天まで昇る心持であったと言います。
それからさらに数年の修業を経て、やっと独立できるようになります。あまりの辛さに半数は消え失せると言いますが、現代人であれば、おそらく一人も残らないのではないでしょうか。江戸の 「華の三職」 の誇りと気概は、この試練を乗り越えてきた “自信” にあるのです。まさに、怖いものなし。「ってやんでい、べらぼうめ!」 なのです。
大工の賃金は一日あたり五四〇文、普通町民の賃金が三百文ですから、すでに倍ちかいわけです。そのうえ実労働時間は四時間程度。早朝・残業(黄昏まで)ともなれば時間外手当がつき、実労十時間なら、賃金は二日分になったと言いますから、大工という商売はやめられなかったのです。また、江戸では頻繁に火事が起こったので、食いっぱぐれもなくひっぱりだこで、笑いが止まらないほど金がふところに入ってきました。当然遊びも派手に、また粋になりました。「江戸っ子は宵越しの銭はもたねえ」 と言われる所以です。
contents
鳶(とび)は昔のアイドル 火事と喧嘩は江戸の華、なぞと昔から申しますが、火事といえば、火消し。火消しといえば、鳶のお兄さん方で、当時はかなりモテタらしいのです。
屋根の上の梯子は「枠火の見」。おおよそ8メートルの高さ。
江戸の消防組織は万治年間(一六五八~一六六一)頃作られたと言われていますが、これを整備したのが、将軍吉宗の享保時代(一七一六~一七三六)で、大岡越前が町奉行に就任してからと言います。江戸の火消し組織は、幕府直轄の定火消し(じょうびけし)、大名直属の大名火消し、町奉行統括の町火消しと、大きく三つに分類できます。町火消しは、それぞれの町々によって編成された大組十番小組四十七組の消防組合でした。時代劇 「暴れん坊将軍」 を思い出していただきたい。たしか、め組に入り浸る徳田新之助とは……。
大名火消しのなかで当時名を馳せていたのが、加賀藩お抱えの加賀鳶(かがとび)です。もっとも、加賀鳶の歴史は相当古く、天和元年(一六八一)には幕府の命令で御三家に加え、加賀鳶の出動記録が残っています。
鳶が火消し役として適任であったことは、その職掌からして明らかで、当時の消防組織で先頭にたって働くのは鳶が主体でした。また、当時の鳶の服装はきわめて派手で、羽織の表(紺地)を着て火消しに当たり、火消しが終わると派手な絵模様の裏を返して、見せびらかしながら町中を練り歩きました。現代版リバーシブルコートのようなしゃれた着こなしをしていたのです。この火消し装束は当時のひとびとにもてはやされ、大店(おおだな)の若旦那が金に糸目をつけずに、浮世絵師に作らせた半纏(はんてん)なども残っています。火消しの衣装は、江戸の「粋」の象徴だったのです。
新門辰五郎着用と伝えられる家事羽織
大体において鳶には伊達者が多く、命をかけて纏(まとい)を振りかざし、鳶口(とびくち)を手に火事場に飛び込んでいく様子のいい男たちは、江戸の女たちの憧れの的でした。黙阿弥(もくあみ)の戯曲「盲長屋梅加賀鳶」(めくらながやうめのかがとび)の主人公、鳶梅吉の女房おすがなど、武家の娘でありながら、実家と縁を切ってまでも梅吉の女房になっています。火消しの人気の高さを物語る逸話でしょう。加賀鳶は加賀藩お抱えの鳶でしたが、江戸の花町でのモテぶりは天下一品だったそうです。さながら、現代のSMAPかV6のようだったのでしょうか……?
蛇足ですが、江戸では正月のお飾り売りは、たいていの場合、鳶の組や仕事師などが、歳末にだけ小屋をかけて商いをしたのだそうです。
contets今なお生きつづける儀式 日本各地の正月行事のなかで、一風変わった行事が行われているのをご存知でしょうか。正月といえば初詣。初詣といえば人でにぎわう拝殿が写し出されますが、そのなかで、一本の材木を前に神官の装束に身を包んだ人物が、見慣れない道具を使ってなにやら真剣な表情をしています。現在では、ごく少数の神社と一部の民間会社がこの儀式を継承していますが、これこそ、建築業界(大工職人)の文化を伝える、「釿始(ちょうなはじめ)」です。
速玉大社礼殿での釿始 日光東照宮本殿上棟式に用いた儀式道具
普通、建築関係の儀式といえば、棟上げ式が馴染み深いものでしょう。また、少し詳しい人であれば地鎮祭などを思い浮かべるに違いありません。今は地鎮祭が起工式をかねることが多いのですが、かつては土工事の始まりにすぎず、木工技術が主流であった当時では、「釿始」こそが起工式でした。ゆえに、知る人ぞ知る、珍しい建築儀式の一つなのです。
この儀式の名称になっている「釿(ちょうな)」は、手斧ともいい、最近ではあまり見かけませんが、材木の表面を削るための工具です。古い民家の大黒柱やの表面が少しゴツゴツとしているのは、「釿」で削った跡で「釿目(ちょうなめ)」と呼ばれています。
現在私たちが言う大工(だいく)のことを、中世以前は大工(こだくみ)とか番匠(ばんしょう)と呼びました。そもそも大工(おおいたくみ)は、古代に工匠一般の指導的地位に相当する官職として定められた呼称で、中世前半までは、鍛冶大工(かじおおいたくみ)というように職人の指導者を指していました。中世半ばから実力者、指導者をあらわす呼称として棟梁(とうりょう)が使われるようになり、「だいく」という言葉は木工職人にのみ残されたのです。
起工式としての「釿始(ちょうなはじめ)」では、工匠の神様を祭り、式後の祝宴は、神と人、人と人との交流の場でした。建設にかかわる人々が一堂に会し、共同意識を高め、工事に取り組む心を一つにする場であったわけです。
近世に入り、「釿始」は年中行事化して、職人たちの正月の仕事始めとして行われるようになりました。職人たちは技術の伝承と向上を願い、工事の無事を祈りました。それが現代まで延々と受け継がれてきたのです。
contents設計図面は私たちの手紙
手書きからコンピュータグラフィックスへひとつの構造物を作り上げるには、発注する人、設計調査する人、施工する人など、多くの人々が参加しています。参加する人の意志を統一する材料の一つとして、設計図面があります。発注する人の希望する物、設計調査する人の意図や企画を、施工する人に間違いなく伝える一つの手紙のようなものと言っていいでしょう。
近世以前の日本では、大工の棟梁が設計する人であり、かつ施工する人でもあったため、詳細な設計図面は不要でした。棟梁の思うがままに仕事が進められ、気に入らない注文をされると、プイっと怒って帰ってしまう棟梁もいました。現代でも大工の棟梁に弁当や酒を振舞いますが、このころの名残りなのでしょうか?
幕末になって、外国人技師が自分の設計意図を伝えるために描いた設計図面が、西洋文明とともに、製図文化を日本に伝えました。その後、日本人の技師達は、こぞって設計製図を勉強し、製図道具を使いこなして図面の表現に熟練していったのです。
さて、明治の製図風景はといえば、製図板に紙を密着させるため、水張りといって、まず紙をぬらし製図板にすばやく貼りつけることから始まります。紙が乾くまでに時間がかかるので、瞑想しながら構想を練る者や、暇つぶしに遊びに出かけてしまう者もあったようです。のんきな時代ですね。設計図は鉛筆で描かれる場合と、鉛筆は下描きで烏口(からすぐち)で清書する場合がありました。青写真の原図は、鉛筆で書かれた図面の上に薄をのせて、トレーサーが烏口でトレースしました。薄美濃紙(うすみのがみ)を通して透けて見える下の原図を、きれいになぞったわけです。美しい線を引くために、烏口の先は常に研ぎ澄まされていなければなりません。烏口の先を研ぐのも仕事の一つでした。また、当時すでに製図用インクはありましたが、ほとんどの人は硯(すずり)で墨をすりました。私たちも学生時代烏口を使って製図をしましたが、墨入れの際の緊張感は今でも覚えています。
昭和4年の英仏独式烏口カタログ CADによる平面図
むかしの青写真は、青地に白い線の陰画でした。これを当時青焼きと呼んでいたのですが、アルカリに弱い欠点がありました。そのため、現場でセメントを含んだ水がかかると、図面が読めなくなってしまうという怖さがあったのです。いまの青写真は、白地に青い線の陽画で、昔ながらに青焼きと呼ばれていますが、現像技術の進歩により、図面が汚れる心配もなく、白地なので書きこみ、着色ができるようになりました。青写真という言葉は、設計図という意味から未来図という意味に転じ、「将来の青写真ができた」などという使われ方をするのはご存知のことでしょう。
昨今はCADやCGが普及し、コンピュータ画面に向かってキーボードとマウスを使って図面を描く作業が主流となっています。トレーサーという言葉は死語に近くなり、キャドオペと呼ばれる人達が台頭してきました。図面の保管も、昔のような保管棚ではなくFDやCDになり、製図室の風景もだいぶ様変わりしました。CADやCGによって、単なる図面作成だけではなく、コンピュータの中で擬似空間を作り上げ、構造物の性能チェックを行うという画期的な仕事が可能になりました。バーチャルリアリティは、もはやゲームセンターの遊びだけではなく、建設業界にとって、なくてはならないものになろうとしているのです。
contents消してはならない建設産業の火
これからの建設産業に思う人間が社会を形成するにあたって、地上に刻みつづけてきた大いなる営みが「建設」です。建設物は先輩達によって作り上げられ、私たちの手で維持、あるいはリニューアルされ、後輩達に受け継がれて行きます。日本は成長期から成熟期に移行してきたと言われますが、その成熟期にいる私たちの課題は、人間性を重視したゆとりのある社会の開発ではないでしょうか。
過去、三度の社会的成熟期が存在したと言われています。第一期は平安時代、第二期は鎌倉時代、そして第三期は江戸時代です。現代はその延長と考えれば、今こそ第四期成熟期と言えるのではないでしょうか。
過去三度の成熟期に共通して言えることは、どの時代も政治的、経済的に安定、あるいは成長していた時代だということ。でも、はたして現在の第四期成熟期が、安定期と言えるのでしょうか。経済危機、雇用不安、何をとっても明るい話題などありません。今日の成熟社会における国際的市場の開放、人々の価値観の多様化は、建設産業に厳しい課題をつきつけています。建設産業に対するイメージからも、「公共投資=建設業界の利潤」という、ゆがんだ認識がひとびとに植付けられていることがわかります。私たちは建設産業に働くものとして、そのイメージの改善に努力しなければなりません。
成熟社会の中で建設産業が目指す方向は、簡単に言えば社会の要求する個性化、地域化にもとづいて、環境の整備を進めていくことにあります。そのためには、弾力的にかつ厳しく、建設環境の改善を進めていくべきです。そして的確に時代のニーズを把握し、社会資本の整備に心がけなくてはならないでしょう。
先輩から受け継いだ輝かしい建設産業の歴史の火を消してはならないのです。一日の仕事が終わったあと、素直に心から「ご苦労様、明日もがんばろう」と言い合えるような、そんな建設産業になる日が再びやってくると信じてやみません。■参考文献
「図説 大江戸の賑わい」西山松之助・高橋雅夫/河出書房新社
「すぐそこの江戸」稲垣史生/大和書房
「江戸時代 町人の生活」田村栄太郎/雄山閣出版
「図説 大江戸知れば知るほど」小木新造/実業之日本社
「江戸の町(上下)」内藤 昌・穂積和夫/草思社
「いすか」№2,3/清水建設㈱ページトップへ